 近年、アクセサリーメーカー製作の単品販売のサックスネックに加え、大手のサックスメーカーもオプションとしての単品ネックのバリエーションを揃え始めています。かつてより「ネックの交換」はサックス奏者の「究極のチューンナップ」の方法のひとつでしたが、今まさにネックの時代が来ているようです。サックスのネックについて研究してみましょう。
近年、アクセサリーメーカー製作の単品販売のサックスネックに加え、大手のサックスメーカーもオプションとしての単品ネックのバリエーションを揃え始めています。かつてより「ネックの交換」はサックス奏者の「究極のチューンナップ」の方法のひとつでしたが、今まさにネックの時代が来ているようです。サックスのネックについて研究してみましょう。
サックスネックの音響的な機能を語る前に、「ブランドのシンボルマークを表示する部分」としてのネックのデザインを見てみましょう。サックス奏者の演奏中の顔のアップの画像では、サックスのネックも大きく表示されます。そしてそこに付いたブランドのマークに憧れて、「僕もセルマーが欲しい」、「彼がヤマハだから私も」、などとサックスを選択した経験はないでしょうか。ネックもしくはネックオクターブキーの中心に、セルマーなら「Sマーク」、ヤマハなら「三本音叉マーク」、ヤナギサワは古くは「竪琴マーク」、今は「YANAGISAWAマーク」、キャノンボールは「Cマーク」、カイルベルスは「JKマーク」等、各社個性的なマークでアピールしています。アルトとテナーでは、ネックはまさにサックスの顔になっています。そういえばアメセル(アメリカセルマー社組み立て)のMark VIやMark VIIのネックマークは、フラセルのものが「Sマーク」の周りがブルーの塗料で埋められているのに対し、アメセルのものは何も塗料が入れられてないのが特徴でした。多くのサックス奏者がMark VIやMark VIIを所有していた時代、高価なアメセルを買えないフラセル所有者の多くが、青い塗料を削り取って「アメセルもどき」にしていました。
 サックスのネックは、サックスの音色と吹奏感に大きく影響を与えることは、今では常識となっています。単品売りのオリジナルデザインのネックは、古くから人気を持続しているものも少なくありません。GlogerやKB SAX、Saxgourmetのハンドメイドネックや、PARASCHOSの木製ネック等は息の長い人気を保っているようです。また近年ではYAMAHAやYANAGISAWA、セルマー等の大手サックスメーカーも、オプションの特殊デザインネックを数多く取り揃えるようになりました。ネックの形状デザインばかりでなく、ネックの素材にスターリングシルバーやハンドハンマーの純銅を使ったり、またフィニッシュのメッキを変えたりと、各社独自の工夫で、独自のサウンドを実現しています。オプションネックは、ちょっと購入をビビるほどの価格のものがほとんどですが、ネック変更の効果はとても大きいようです。
サックスのネックは、サックスの音色と吹奏感に大きく影響を与えることは、今では常識となっています。単品売りのオリジナルデザインのネックは、古くから人気を持続しているものも少なくありません。GlogerやKB SAX、Saxgourmetのハンドメイドネックや、PARASCHOSの木製ネック等は息の長い人気を保っているようです。また近年ではYAMAHAやYANAGISAWA、セルマー等の大手サックスメーカーも、オプションの特殊デザインネックを数多く取り揃えるようになりました。ネックの形状デザインばかりでなく、ネックの素材にスターリングシルバーやハンドハンマーの純銅を使ったり、またフィニッシュのメッキを変えたりと、各社独自の工夫で、独自のサウンドを実現しています。オプションネックは、ちょっと購入をビビるほどの価格のものがほとんどですが、ネック変更の効果はとても大きいようです。
テナーサックスのネックは曲がり易いと言われています。美しい曲線の長いネックは、演奏中のサックスの挙動や、ちょっとしたアクシデントによって、テコの原理で角度が変わってしまうことがあります。下方向に曲がったネックは、「ネックがお辞儀してる」として、修理が必要です。そのままだと設計通りの音程性能が出ません。しかし決して自分で、力づくで戻そうとしないでください。ネックは曲がるとパイプの真円性が損なわれ、断面が楕円になります。そこを無理に戻せばまだ歪みが酷くなります。ネックの矯正は、かなり難易度の高いリペア技術です。スターリングシルバーなどの柔らかい金属で作られたテナーのネックは、多くの場合支柱のステーやガードプレートで曲がりを防いでいます。そのステーやガードプレートの重さによっても、吹奏感やサウンドが変わるようです。
——————————————————————————————–
⇒『 AIZENより Summerキャンペーン 返品保証30日+豪華3大特典付き』
⇒『AIZENお客様の声キャンペーン!』

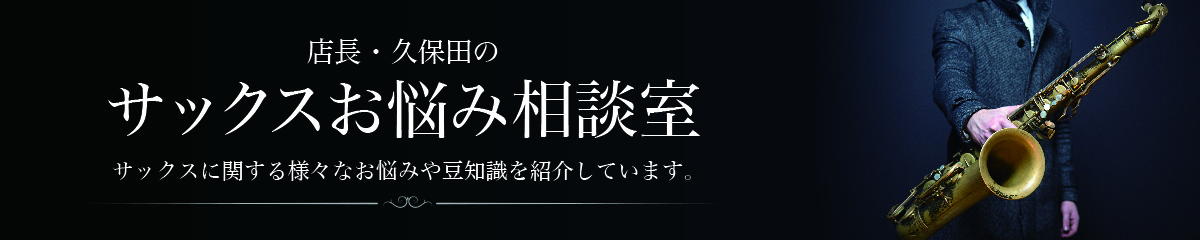


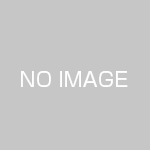



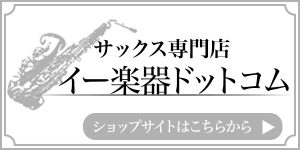
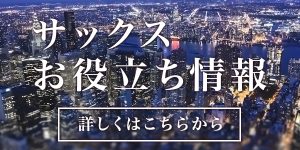






この記事へのコメントはありません。