 サックスばかりでなく、管楽器の中には必ず水分が溜まります。トランペットのウォーターキーを「つば抜き」と呼んだり、床に水分を垂らさぬようスタジオに用意された、水受け皿を「つば皿」(ジャズ系奏者は「ばーつ皿」と呼びます)などの名称から、「管楽器の水分は“つば”」と勘違いしている方も多いようですが、管楽器に溜まる水分のほとんどは、奏者の吹き込む息に含まれた水分が、楽器の中で結露して水になったものです。サックスの中の水分との付き合い方を考えてみましょう。
サックスばかりでなく、管楽器の中には必ず水分が溜まります。トランペットのウォーターキーを「つば抜き」と呼んだり、床に水分を垂らさぬようスタジオに用意された、水受け皿を「つば皿」(ジャズ系奏者は「ばーつ皿」と呼びます)などの名称から、「管楽器の水分は“つば”」と勘違いしている方も多いようですが、管楽器に溜まる水分のほとんどは、奏者の吹き込む息に含まれた水分が、楽器の中で結露して水になったものです。サックスの中の水分との付き合い方を考えてみましょう。
一番最初にサックスに溜まる水分は「リードの上」です。そのまま吹き始めると、「じゅるっ」というノイズが音に入るので、吹く前に指でリードを軽く弾くのがかつては常識でしたが、最近ではあまり見ません。吹き始める前に「ふっ」とカラの息を入れればリードの水分は跳びますから、弾く必要はあまりないかもしれません。次の困った水分は、左手人差し指や中指あたりのトーンホールから滲み出してくる水分です。いつもではないのですが、時々、指がびしょ濡れになるほど出てくる時があります。サックスの管体の角度と、結露した水分の通り道の具合で、このあたりのトーンホールから水分が漏れてくるのは、「サックスあるある」です。今は生産されていませんが、グローバルのサックス、IO(イオ)セライバフリーモデルは、管内に磁石で金属棒を吸着させる事で、水分の流れをコントロールし、左手トーンホールの水漏れを防ぐ、「セライバフリー構造」を採用していました。サックスを立てぎみ、そしてやや左傾斜に構えれば、左手への水漏れがほとんど無くなることから、この機構はやがて消えていってしまいました。もしあなたが左手への水漏れに悩んでいたら、サックスの構え方を少し変えてみてはいかがでしょうか。
 サックス奏者が一番気を遣う「水分」は、練習や演奏後の「パッドの水分の除去」でしょう。サックスは「吹く」ことによって、奏者の息の水分で管体内は「湿度飽和状態」になります。管体の内側はもちろん、トーンホールを塞ぐ「パッド(たんぽ)」もすべて「びっしょびしょ」になります。パッドは柔らかな天然皮革(合成皮革の場合もあり)で作られていますので、水分を良く吸います。吸った水分で柔らかくなり、トーンホールの密閉度もにも貢献するのですが、水分びしゃびしゃのままで乾燥させてしまうと、表面がゴワゴワになります。そんなパッドの「びしゃびしゃ-ゴワゴワ」サイクルを繰り返すと、パッドの寿命は短くなってしまいます。そのため「まじめな」サックス奏者は、演奏の後には必ずパッドに付着した水分を「給水ペーパー」等で吸い取り、管体内にはスワブを通し、しっかりサックス全体をドライな状態にして保管します。最近では吸水性の高いマイクロファイバークロスで出来た、繰り返し使用できる「パッドドライヤー」や、マイクロファイバーを使ったスワブも数多く出回っています。演奏中に楽器の底に溜まった水分は、高分子吸収剤を使った吸水シート、「ステージシート」や「ウォーターシート」等にこぼして吸収させましょう。不用意に床にこぼすと、誰かが滑って大事故になるかもしれません。水分との上手な付き合い方は、管楽器奏者に必須のマナーとエチケットです。
サックス奏者が一番気を遣う「水分」は、練習や演奏後の「パッドの水分の除去」でしょう。サックスは「吹く」ことによって、奏者の息の水分で管体内は「湿度飽和状態」になります。管体の内側はもちろん、トーンホールを塞ぐ「パッド(たんぽ)」もすべて「びっしょびしょ」になります。パッドは柔らかな天然皮革(合成皮革の場合もあり)で作られていますので、水分を良く吸います。吸った水分で柔らかくなり、トーンホールの密閉度もにも貢献するのですが、水分びしゃびしゃのままで乾燥させてしまうと、表面がゴワゴワになります。そんなパッドの「びしゃびしゃ-ゴワゴワ」サイクルを繰り返すと、パッドの寿命は短くなってしまいます。そのため「まじめな」サックス奏者は、演奏の後には必ずパッドに付着した水分を「給水ペーパー」等で吸い取り、管体内にはスワブを通し、しっかりサックス全体をドライな状態にして保管します。最近では吸水性の高いマイクロファイバークロスで出来た、繰り返し使用できる「パッドドライヤー」や、マイクロファイバーを使ったスワブも数多く出回っています。演奏中に楽器の底に溜まった水分は、高分子吸収剤を使った吸水シート、「ステージシート」や「ウォーターシート」等にこぼして吸収させましょう。不用意に床にこぼすと、誰かが滑って大事故になるかもしれません。水分との上手な付き合い方は、管楽器奏者に必須のマナーとエチケットです。
——————————————————————————————–
⇒『 AIZENより 夏得キャンペーン♪ 返品保証30日+豪華3大特典付き』
⇒『AIZENお客様の声キャンペーン!』

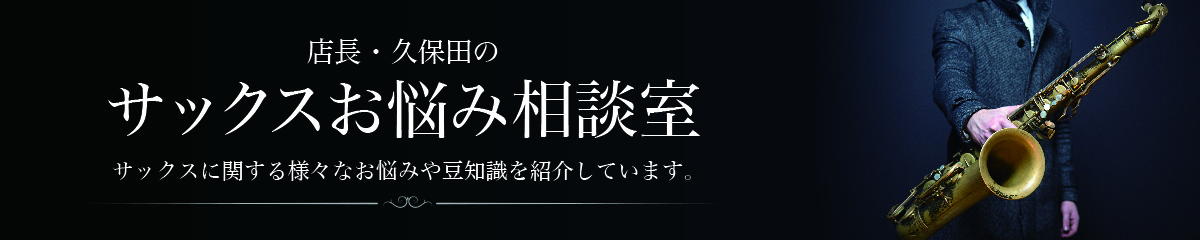


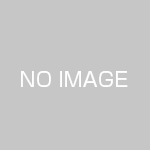




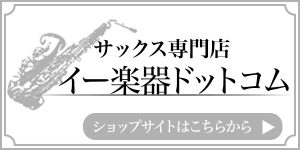
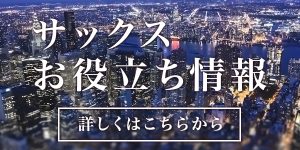






この記事へのコメントはありません。