 大手サックスメーカー、周辺アクセサリーメーカーばかりでなく、専門メーカーまで出て来たサックスの「ネジブーム」は、益々盛況のようです。実はこの類の音質改善は、大昔のサックス奏者もおこなっていた、結構伝統的な手法です。
大手サックスメーカー、周辺アクセサリーメーカーばかりでなく、専門メーカーまで出て来たサックスの「ネジブーム」は、益々盛況のようです。実はこの類の音質改善は、大昔のサックス奏者もおこなっていた、結構伝統的な手法です。
サックスほど、多くのサウンドの改造手法が試されている管楽器は他に類が無く、それだけプレーヤーが音質や吹奏感に敏感で、かつ各種の努力や工夫で何らかの確実な変化が得られるということでしょう。そのなかでもサックスの音質改造に、響きの倍音の足し算と引き算を利用する、という伝統的な手法が今も受け継がれています。
ネックスクリューやライヤースクリューに特殊な金属のものを使用する、今流行りの「特殊ネジ」は響きの足し算にあたると考えられます。共振する金属素材を取り付けることによって、サックス管体の響きの周波数分布を能動的に変え、サックス全体の響きの特性を変えてサウンドを変化させています。一般的に硬い金属を使うほど、サウンドがシャープになる傾向があるようです。
 古くから使われている方法、「鉛の貼り付け」は、倍音振動を部分的に吸収し、減衰させる響きの引き算です。ちょっと昔のサックス界では、鉛を平たく延ばした釣り用の「板鉛」を、両面テープや接着剤でサックスの色んな場所に貼り付けることで、サウンドの調整をしていました。
古くから使われている方法、「鉛の貼り付け」は、倍音振動を部分的に吸収し、減衰させる響きの引き算です。ちょっと昔のサックス界では、鉛を平たく延ばした釣り用の「板鉛」を、両面テープや接着剤でサックスの色んな場所に貼り付けることで、サウンドの調整をしていました。
一番流行った例がU字管への取り付けです。この処置によってサウンドが締まり、音の抜けが良くなると言われていました。実際、セルマーのヴィンテージサックス、「アメセル(アメリカで再組み立てされたセルマーのサックス。SBA、Mark VI、Mark VIIの時代のみ)」のなかには、U字管の内部にオモリがハンダ着けされているものもあったそうです。
次に多いのが低音域C以下のトーンホールを塞ぐカップへの鉛装着です。低音部のトーンホールは穴の径も大きく、空気が逃げようとする力も強いので、オモリを付けて振動を抑えることで、低音域が安定するそうです。この処方は実際にプロのリペアマンも施す場合もあるようです。
低音域でのフルブロー(目一杯に息を吹き込んだ状態)で音がフラッターを起こす場合は、カップに鉛を着けてフラッターを止める方法もあるそうです。最近でもたまに見かける「鉛テクニック」は、ネックのネックコルク手前の部分に板オモリを巻きつける処方です。何周か重ね巻きをして、ある程度の重量を付加します。板オモリより重い、金属製のブロックをネジ止めするアクセサリーも販売されています。サウンドのフォーカスが締まり、音が太くなるといわれています。
サウンド改造ネジ等のアクセサリー類は決して安くはないものが多いですが、板鉛は100円ちょっとでごっそり買えます。以前紹介したように、ネジを自分で削るのも良いかもしれません。お金を掛けずに自分のサックスを改造して、新たなサウンドを追求するのも楽しいですよ。あ、くれぐれも元に戻せるように、慎重に改造してくださいね。
——————————————————————————————–
⇒『 AIZENより 春の感謝キャンペーン! 返品保証30日+豪華3大特典付き』
⇒『AIZENお客様の声キャンペーン!』

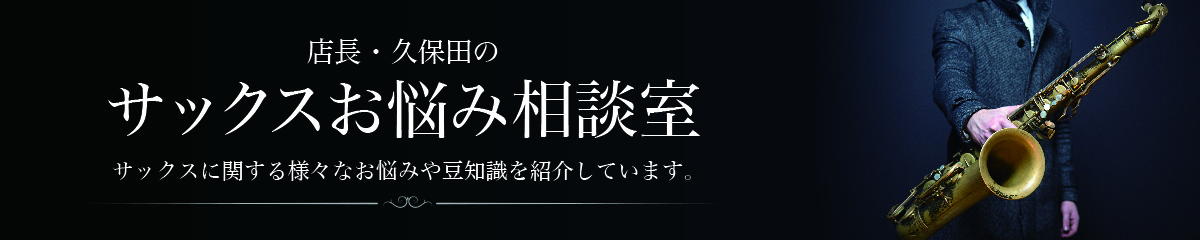


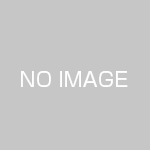



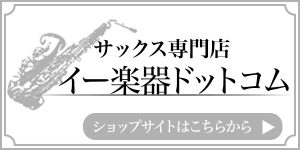
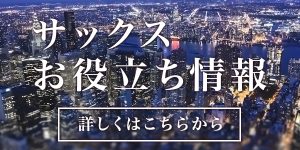






この記事へのコメントはありません。